春休みの友
【Ⅰ】
ぼくの記憶はてんであてにならない。
意識の底をまさぐってみると、色あせた心象風景が幾重にも折りかさなっている。木造だった小学校の校舎だとか、糠拭きで飴色に光る廊下だとか、ポプラの葉で埋めつくされた秋のプールだとか。風景はスナップ写真のように固定化されていて、想像力を駆使して動かそうと試みても画柄はほとんど変化しない。中学校にあがったころから、停まった風景はようやく動きはじめるが、それでも画のはしばしがあいまいなのである。
これから読んでいただく一日のできごとは、思い起こせる範囲の中ではいちばん古いたぐいのものだ。これを書くにあたって詳細をたしかめるため、郷里の熊本に住むふたりの旧友に電話をかけた。ところが、彼らの記憶もまたさだかではなかった。
「三人で一緒に大牟田へ行ったろ? 覚えとるや」
「ああ、覚えとるばってん、いつだったかね……」
ぼくは夏休みだと思いこんでいたし、魚津もまた同意見だった。しかし明石は違うという。
「よそは知らんが、熊本県の教育実習生の研修期間は二学期たい? 翌年の夏休みだとすると、あいだが空きすぎておらんや」
「でも、あの日は蒸し暑かった気がする」
「おれもやたらと汗をかいた気がする。となると冬休みはありえんね。春休みだったと思う。いずれにせよ夏休みじゃなかよ。中二になったらおれたち、べつのクラスだったけん」
現役の教員である明石の意見には説得力があった。では、季節は〈春〉ということにしよう。
「ところで、教育実習生の名前は思いだせん?」
「なんて名前だったかねー。実家に帰って押入れの中を探せば、その人から届いた年賀状くらい見つかるかもしれんが……」
同じ質問を魚津にぶつけると自信なさげに答えた。
「たしか下の名前は、あや子先生だったと思う」
「名字は覚えとらんや?」
「さあ、姓は忘れた」
と、すげない返事だった。思いだせないならしかたない。ここはひとつ魚津の証言を頼りにしよう。一年四組のときの教育実習生は〈あや子先生〉だ。
このように記憶とはあてにならないものだ。ふたりともうろ覚えだったが、中学時代をいちいち懐かしがっていたら日々の暮らしはおぼつかない。ぼくにしてもこのことは忘れかけていた。掌編をものにしようと目論まないかぎり、思いだそうともしなかっただろう。
【Ⅱ】
春休みになったら、教育実習生だったあや子先生に会いに行く、大牟田のお宅に訪問するするつもりだと伝えると、ぼくの両親はあまりいい顔をしなかった。が、魚津遼二くんと明石正志くんが一緒だとつけ加えたら、学生服着用を条件に大牟田行きを認めてくれた。
銀水行きの普通電車は、午前一〇時半すぎに熊本駅を発車した。日帰りとはいえ中学生だけで県外に出るのは初めてだった。気持ち弾んで、浮かれるのがあたりまえだのに、どうしたことか三人とも言葉少なだった。たまらずぼくは車窓を引っ張りあげて、外の風を迎えいれた。ここは無人駅だろうか。ひとけのないホームに〈田原坂〉の駅名を掲げた看板がぽつねんと立っている。西南の役の古戦場。各停が大牟田に到着するまであと三十分はゆうにかかるだろう。
向かい合わせた席の明石が、ぼくの隣に座った魚津にたずねた。
「その紙袋のなかにはなんが入っとると」
「アルバム。あや子先生は洋楽好いとらしたけん、『緑の地平線』ば手みやげに選んできた」
「よそのお宅にお邪魔するとだけん、うちのひとに喜ばれるようなおみやげ買うて行かんと。駅の売店で、お菓子かなんか買わんや」
「なんや、おれの選んだプレゼントに異論あるごたるね」
「異論じゃなかばい。なんか子ども子どもしとらんや?」
「要するに、おれが子どもじみとるといいたかわけたい」
「そがんこた、いうとらん」
一事が万事こんな調子で、車内の雰囲気はいっそう険悪になったが、ぼくにはどうすることもできなかった。ふたりの忙しい会話に乗り遅れてしまうのはいつものことだった。
あや子先生に対する魚津の態度はやや度が過ぎていた。
こんな授業内容では教員に採用されませんねえと、校長みたいな口調でいやみをいい、まじめに掃除しなさいと注意されようものなら先生も掃く手を休めんでくださいと即座にやり返していた。ぼくも魚津の尻馬に乗って先生をからかった。もっともクレバーな彼とは違って、服がイモだのおかちめんこだの、他愛ない悪口を吐くのが関の山。もちろん本心ではなかった。なんとか先生の気を惹こうと躍起になっていただけだった。
心ない言動に、先生がどれだけ傷つこうとおかまいなしだった。明石が指摘するように、まったく子どもっぽいふるまいだった。
しかし先生は寛容だった。質の悪いからかいになかば呆れつつ、笑って聞き流してくれた。だからかあや子先生といえば笑顔、いつもニコニコしているの印象がつよかった。
二週間の研修期間が過ぎて、先生が大学に戻ったあとで、ぼくはようやく自分の過ちに気づいた。あんなこといわなきゃよかったと後悔の念しきりだった。それは魚津も同じ気持ちのようだった。
「やましさやらなかばってん、先生にはちょっと言い過ぎたけん」
一方の明石は、年賀状や手紙を出して、先生に連絡をとり続けていた。彼は、魚津やぼくのように先生をからかわなかったのだが、先生にご迷惑をかけたので謝りたいと書いたそうだ。すると、三学期が終了するまぎわに、先生からこんな内容の返信が届いた。
《いちどみんなで大牟田へいらっしゃいませんか?》
そこで、手紙を読んだ三人は、先生に無礼したことをお詫びしに行こうと決心したのである。もっとも、お詫びというのは行くための口実にすぎなかった。久しぶりに先生と会うのが楽しみだったし、仲間と連れだっての遠出に胸が躍った。ところが、いざ当日になってみるとなんとなく気が進まない。目的地が近づくにつれて口数はますます減っていく。こうして三人が煮つまっているうち、電車はとっくに県境の荒尾を通過しており、次の停車駅に向かって減速中だった。
「おーいここだよー」
大牟田駅の改札を出たところで、あや子先生が手を振っていた。実習期間中と変わらない柔和な笑顔だった。髪にゆるやかなウェーブがかかっている。最近パーマをかけたのだそうだが、あまり似合っていなかった。
「長旅のところすみませんが、これからもう一本、バスに乗ってもらいます」
「ウェーッまたや」
傍にいた魚津が、喚いたぼくのわき腹にズンとこぶしを入れた。
駅前広場の時計塔が、まもなく正午を指すところだった。先生を含めた四人は三池行きの西鉄バスに乗りこんだ。道中どんな会話があったのか、よく覚えていない。ふたりの緊張が伝染して、ぼくも喋るのが億劫になって、外の景色ばかり眺めていたのだろう。
大牟田の景色は熊本とはずいぶんようすが違った。
白っぽい色あいの町並みを縫うように国鉄の引込み線が何本も走っている。鋳物かなにかの工場だろうか、煉瓦造りの古い建物が目立つ。とくに赤白だんだらに塗られた集合煙突は熊本ではお目にかかれないものだった。
大牟田は四日市とならんでぜんそくの被害が甚大であると、新聞を読んで知ってはいたが、ただちにバスに乗ったせいか、息苦しさはさほど感じなかった。
二十分ほどバスに揺られて、終点三池のロータリーに着いた。
なだらかな傾斜の小径をしばらく歩くと、すぐに舗装がとぎれてじゃり道にかわった。道なりに小川が流れている。水の流れは急で心なしか黒ずんでいた。炭鉱は近くですかと明石が訊くと、先生は小高い山を指差して、この裏手に三池炭鉱があると答えた。稜線を跨いだ高圧電線が弓なりにたわんでいる。ねずみ色した厚ぼったい雲が山頂の空をおおっており、銀色の鉄塔のみが鋭く輝いていた。
道の突きあたりの、ちょうど家並みがとだえたところに、あや子先生のお宅が控えていた。魚津の記憶によると、緑色の瓦屋根が印象的な平屋建て、だった。
玄関先には上品そうな初老の婦人が待ちかまえており、まあまあよくいらっしゃいましたねと相好を崩した。先生そっくりの穏和な微笑みだった。先生は自分の母親に三人の教え子を紹介した。
「出席順に、明石正志くん、岩志田京資くん、魚津遼二くん」
「遠いところをわざわざ。なんもおかまいできませんけど、どうぞごゆっくり」
先生のおかあさんがいったん奥に引っこむと、しまったと魚津がつぶやいた。明石の言い分が正しかった、手ぶらでよそさまの家にあがるのは失礼だったと悔やんでいた。
三人は玄関を入ってすぐの、革張りのソファーが据えられ、トロフィーや盾、ウイスキーやブランデー、百科事典やアルバムが壁一面の洋棚に並ぶ、応接間に通された。
そこでさっそくお昼をいただいた。ちらし寿司とおすましという心づくしのごちそうだった。三人はしきりと恐縮しながら、とてもおいしいのでめいめいお代わりしたところ、おかあさんはたいそう喜ばれ、食後には紅茶と亀屋の丸坊露が出てきた。ひとごこちついたぼくたちは、ようやくわれにかえって、本来の目的を思いだした。
「これ、先生に……」
と、魚津がきれいに包装された正方形のプレゼントを手渡した。さっそく包み紙をほどいた先生は、あっカーペンターズ大好き、と顔をほころばせた。三人はホッと安堵の息をついた。
「でも、LPは高かったでしょ、もらっちゃっていいのかな」
「よかです。おれたち、先生に迷惑ばっかりかけよったけん」
これは魚津なりの謝辞だと思って、自分もなにかいわなければと焦ったが、話すきっかけを逃してしまった。ぼくは曖昧な笑みを浮かべてみんなの会話にやたらと相づちをうった。これでも自分なりにせいいっぱい謝意を示したつもりだった。
明石は率先して最近のクラスのようすをあや子先生に伝えようと、誰それはどうしている、こんなことがありましたと熱心に報告していた。しかしいまは春休み、あと十日も経てばぼくたちは二年生である。興味ぶかげに耳を傾けている先生にしても、研修で受け持ったクラスの印象などだいぶ薄れてきているだろうに。ぼくはふたりのやりとりをいくぶん冷ややかにみていた。
「音楽でも聴こうか。魚津くんはポピュラー好きだったよね?」
レターメンなんてどうかしらとつぶやきながら、先生は旧い型のステレオのスイッチを入れた。音楽がかかると、いい感じですねと明石はうなずいていたが、すでにハードロックの洗礼を受けていた魚津は、品行方正な男性三重唱に渋い表情をした。ぼくにしたってしらじらしい時間がこれ以上続くのはカンベンだった。
そろそろおいとましたほうがよかないか?
そう考えていた矢先、先生はだしぬけにこんな提案をした。
「ねえ、せっかく福岡に来たんだもの、みんなをステキなところへ案内したいな」
それから奥の間に向かって、おかあさんと呼びかけた。
「いまから出かけてくるけん」
「あらあら水ようかん切ったとに。あや子ちゃんな、どこへ連れていくつもりね」
怪訝そうな面持ちの母親に、娘は快活な声で返した。
「ちょっと、柳川まで」
時刻はすでに午後一時半を過ぎていた。ぼくは帰りの時間が気になってしかたがなかった。
「大牟田から柳川まで、けっこうな距離あるでしょう」
「心配ご無用。西鉄特急で十五分、あっという間だから」
大牟田駅に着くと、先生は四人分の切符を買って、いちばん奥のホームへ向かった。ま新しいツートンカラーの特急電車は、四人の搭乗を待ちわびていたかのようにすぐさま出発した。なるほど特急の名に恥じない走りっぷり、それでいて普通電車と同じ運賃、福岡の交通事情は進んでいるなと、ぼくはすっかり感心した。
西鉄柳川の駅前に降りたつと、大きな町じゃないから歩こうかといって、先生は先頭に立ち、はりきって歩きだした。しかたなしに三人は、そのあとをぞろぞろとついていった。
人口四万の柳川はむかしながらの風情をいまも残す、落ち着いたたたずまいの城下町である。
川下りの船着場を左に折れると水郷のイメージに違わぬ掘割の風景が展開しはじめる。大小さまざまなクリークが縦横無尽に町の中を流れて、蔵屋敷の白い壁としだれ柳の緑が水面に揺れている。
狭い路地の角っこを幾度となく曲がって、お寺や味噌蔵を何軒かやりすごし、堀に架かる石橋を何本か渡り、柳川高校、柳川城址を横目にしながら、埃っぽい県道をさらに西へ進む。が、二十分ほど歩いているうち、腋に背中に、じわりと汗がにじんできた。
「先生、いったいどこまで歩くと?」
もう少しガンバレと答える先生の額にも、玉の汗が光っていた。
「あ、あれが御花ね。旧立花藩の別邸だった」
明治時代の建造だろうか、瀟洒な白亜の洋館が曇天の下に威容を誇っていた。
「この洋館の奥には日本庭園や、天皇陛下も泊まったという旅館や料亭があって」
「ふーん……」
興味のないぼくはいい加減な返事をした。そのへんに座りこんで休みたいと思っていたところ、先生は水天宮の曲がり角を左折したところで、ようやく歩みをとめた。
本日の目的地はここです! と先生が高らかに宣言したそこは、詩人・北原白秋の生家だった。
いまでこそ改築してりっぱな記念館が併設されているけれども、かつての「白秋生家」は、白秋が生まれ育ったころの面影を色濃く残したままの、詩歌に興味ない中学生の目からみれば、単なる古ぼけた家屋だった。入ってみると館内はうす暗く、湿った空気はかび臭く、どことなく陰気な印象を受けた。
けれども、その陰気なたたずまいが三人の好奇心を刺激した。
ガラスケースに収められた『思ひ出』の草稿や愛用のペンなどの展示物を、もっともらしくうなずきながらつぶさに見学し、さらに海産物問屋だったという屋敷じゅうを、それこそ少年時代のトンカジョンよろしく、くまなく探索した。黒光りに艶めく板張りの間の奥の、急な階段をよじ登って二階へいたれば、天井に架かる梁はあたまにつかえるほど低く、その閉塞した空間に身を置いていると、なんだか秘密の隠れ家に紛れこんだみたいにわくわくしてきた。
さらに奥には屋根裏部屋ともいうべき狭い部屋があった。部屋の中央にこぢんまりした座卓があって、それは白秋が思索――詩作にふけるさいに使ったものだという。また、座卓の脇には雑記帳が何冊か積まれている。訪ねた人々が思い思いを書き記すのだろう。
「おれたちも記念に一筆書いておこうや」
と、魚津が大人っぽい口をきいた。
〈七五年三月・熊本市・魚津遼二〉
こういうとき彼は、必要最小限しか書かない。
〈ここに来て少しだけ白秋の詩情がわかる気がしました〉
明石はやや多めに書いた。おー優等生と魚津は軽口をたたいた。ここにきて魚津もようやく本来の自分を取り戻したようである。書き終わったふたりは冗談を交わしながら階下に降りていった。
ひとり残ったぼくはサインペンを掌に転がしながら、さあなんて書こうかと考えあぐねていた。ところが敷居を跨いだあたりにあや子先生が立っていて、ぼくを見下ろしているではないか。
「魚津くんと明石くんは?」
「表に出てサイダーば飲もうて、いまさっき相談しよった」
「岩志田くんは一緒に行かないの?」
「おれ、これ書きあげな」
先生は座卓のま向かいに腰を下ろした。そこに座られるとなんか書きにくかと抗弁しても無駄、まるで試験監督官みたいに、ぼくが書きあげるのをじっと見守っていた。
なにを書いたのかは覚えていない。雑記帳は保管されているのだろうか。万が一残っていたとしても読みかえしたくない。いたずら書きではなくまじめなことを書いたはずだが、それでも三十年前の文章に再会したら、きっと赤面してしまうだろう。
「せっかくだし、あたしも書こうっかな」
座る場所を入れ替わり、さくら色した自前の万年筆を取りだした先生は、柳川と白秋の印象をさらさらと綴った。内容の詮索を遠慮していたが、末尾の一行、〈来年こそ教員になれますように〉を見つけてしまったぼくは、つい冷静ではいられなくなった。
「先生、採用試験は不合格だったと?」
「うーん、残念ながら本年度は逃しました」
先生の態度は妙にさばけていた。
「臨時採用に応募したから、四月から地元の中学に通うけど」
ぼくは自責の念にかられた。もしかして先生の採用が見送られたのは、教育実習の成績が悪かったせいではないか、と。
「ぼくらの態度があんまりひどかったけん、それが原因で?」
「違うちがう。そんなんじゃない。単にあたしの勉強不足」
ぼくの口吻をさえぎるように、穏やかな口調で語りかけた。
「じつはうちの両親、あたしの教職志望に消極的だったの。そげん無理して教員にならんでもよかろうと。でも、今日きみたちが来てくれてうれしかった。なんてたって教え子が訪ねてきたんですもの、母の見る目も変わって、これからは好意的になると思う」
ぼくは先生を正視できずに、額縁くらいの小窓から射しこむ光をみつめた。けれども目に入るものは低く垂れこめた雲ばかり。そればかりか、遠くから聞こえてくる和太鼓の乱打みたいにくぐもった音は、雨の降りだす前ぶれにほかならなかった。
「あら雷さま? あのふたり、外にいてだいじょうぶかな」
いましがた覚えたばかりの第一詩集の題名、『邪宗門』が脳裏をよぎった。
【Ⅲ】
ここでいったん筆を置く。ひとつのエピソードを入れるか否かで迷っていた。じつは明石からこんな電話がかかってきたのである。
「昨晩ずっと、大牟田へ行く理由をいろいろ考えてみたったい」
ぼくからの質問は、明石なりに気がかりだったようだ。
「それで、例の煙の事件を覚えておらんや?」
「煙? いったいなんのことや。教えてくれ」
明石が語ったことを簡潔にまとめると、このようになる。
《土曜日のロングホームルーム(当時は週休二日ではなかった)、一年四組で教育実習生の送別会が催された。歌あり寸劇ありで盛りあがるなか、事件は起こった。クラスの女子が家庭教室で調理した、食パンにバタークリームを塗ったくった不味そうなやつに不恰好なロウソクが立ててあったが、担任がそれに火をつけるなり、白い煙がもくもくと噴きだした。教室内はたちまち煙で満たされるわ、ケーキがだいなしだと女子は騒ぐわで、大混乱に陥った。会は急遽中止となった。自分がしましたと、誰も名乗り出なかったため、クラス全員、担任からしこたま叱られた。そして、職員室に待機させられた教育実習生は、とうとう教室に戻ってこなかった》
まさか! ぼくは思わず大声をあげていた。
「そげん事件ならハッキリ覚えとるはずぞ。一の四の教室だろ?」
「まだ新校舎が建っとらん、プレハブ教室のときたい」
それから、明石はじつに気まずそうな声で、あとを続けた。
「それで……ロウソクば作ったとは……魚津じゃなかったかね?」
「なんて?」
絶句した。どうして魚津が嫌疑をかけられなくてはならない?
「魚津や岩志田は、先生にけっこう悪口ば叩きよったろ? ふたりが結託してロウソクに仕掛けたんだと、そげんうわさが女子中心に広まっとった。根も葉もないうわさだと思いたかよ。でん、そう考えると大牟田まで謝りにいった理由も、腑に落ちると思わんね?」
冗談じゃない。真偽をたしかめようと折りかえし電話をかけた。もちろん魚津はこの件を否定し、心外だと口にした。
「それ、ぬれぎぬだけん。事実なら素直に認める。ばってん、まったく覚えのなかもん。にしても、明石はなしてそぎゃんこというかね」
「先生に対するおれたちの態度が、あんまりだったけんだろう」
「ああ、ずいぶん痛烈にからかったし、ちょっかいもだした」
「覚えとるや。クリップをまっすぐ伸ばして、最後のカーブだけを残して、輪ゴムにそこを引っかけて飛ばす仕組みのパチンコを考案したろ? あれで女子の足元とかを狙いよったけん、恨みをかってもしかたなかろうね」
「……まあ、それにしたって、先生は狙っておらんけん」
「魚津の考案する天才的なイタズラを、おれは尊敬しとったよ」
「頼むから、そぎゃんこと小説に書かんでくれよ。万が一それが人目に触れたら、おれは外を歩けんごつなるけん」
申しわけない魚津、ぼくはこうして書いてしまった。
というのもぼくは、煙の事件は明石の記憶違いだと思うからだ。こういったら失礼かもしれないが、教員生活の長い明石よ、それはきみが教師になってからの経験じゃないか、と疑ってしまうのだ。
なるほど魚津は三人中いちばん成績がよかったうえ、少しばかり皮肉屋の側面はあった。が、心根は優しいやつだ。きみのいう事件がかりにあったにせよだ、魚津は悪質なイタズラをやるような男じゃない。
しかし友よ、ここでぼくは告白しなければならない。
魚津の潔白を信じる一方で、この話に飛びついてしまった。
《しめた。こいつは使えるアイディアだ。駄菓子屋で買った煙玉をロウソクの中に仕込むことにしよう。ふたりへのコンプレックスや対抗心をバネに、ぼくがこしらえたことにして。このエピソードを起点に話を展開すれば、きっと面白い短編小説に仕上がるぞ。『邪宗門』の書かれた部屋で、邪なおのれの心に気づき、あの事件の犯人はぼくですと先生に告解しようとするが、ことの真相を伝えられずに、後悔したまま熊本へ帰っていく……と》
こういう筋書きで一気に書きあげた。ところが仕上がった原稿を読みかえしてみたところ、送別会のシーンだけが妙にあざとく感じた。そのうえパートナからは、じつに痛いところを突かれた。
「どうやったらロウソクの中に煙玉を仕込むことができるの?」
じつは先日、家族と一緒に造形体験教室に参加した。クラフト好きの子につきあって、カラフルなロウソクを製作してみた。亀山ロウソクを何本も折って粉々にし、湯せんで透明になるまでロウを溶かし、それにクレヨンをすり潰して混ぜ、色のついたその液を慎重に卵の殻に注ぎこむという、けっこう複雑な工程だった。学生のインストラクターが指導してくれたおかげで、二時間後には鮮やか色した卵形のロウソクが三個できあがったが、さて、煙玉仕込みのロウソク作りという根気のいる作業、はたして誰の手助けなくして中一の少年に可能だろうか? ぼくは無理だと思う。なんだかんだいって、ぼくも魚津も面倒くさがりなのだ。
ところで、これは自業自得なのだろうが、ぼくは書きあげたあとでいわれのない罪悪感にさいなまれた。
主人公である〈ぼく〉は煙玉仕込みのロウソクを製造したと、ふたりにも先生にも隠していると設定したのだが、その後ろめたい気持ちを描こうと腐心しているうちに、なんだか本当に自分が事件をやらかしたような心境に陥ってしまったのである。
小説とはいえ、事実と違うことを書いていいのかどうか迷った。これは過去をねつ造する行為ではないか。自分の都合のいいように事実をねじ曲げたり、やってもいない事件をでっちあげたりして作品を面白おかしくするのは、してはならないことではないかと。
ちょうどそのころ、ときの首相が靖国神社に参拝した。
その是非をここでは問うまい。ただ、過去を題材にして書くのを悩んでいた時期と、終戦記念日が重なっただけに考えさせられた。周辺諸国にたいして国家としての責任は果たしたと声高に主張する政治家と同様、過去は、物語としていかようにでも書き換え可能であり、手前勝手に改ざんできるものだと身をもって思い知った。
さあそこで、これから残りを書くにあたって、ぼくはできるだけ潤色を避けようと思う。記憶と記憶の隙間を埋めるための、姑息なエピソードをこしらえないように心がけたいし、また、そのことで小説の体裁が悪くなろうと、ぼくはいっこうにかまわない。
【Ⅳ】
春雷のとどろきがひたひたと近づいてきた。時おり青白い閃光がほとばしり、そのたびに先生の横顔を鮮やかに照らしだす。やがて瓦屋根を弾く音がパラパラと聞こえてきた。
それはまるで、ぼくの動揺を見透かすような、優しげな声だった。
「あのね、岩志田くん。大学に戻って、きみたちの悪ふざけを誰かれかまわず訴えたの。あたし実習した先でこんな仕打ち受けたって。いまどきの中学生はひどい。ぜんぜんかわいげがないって」
「……」
「ところがその話をすると、みんなのけぞって笑っちゃうんだな、これが。笑うばかりか妙に感心したり、うらやましがったりする。あるともだちなんか、こんなこといってた。
『いいな生徒から慕われて。おれなんか二週間、ずっと無反応だったんだぜ。でもさ、それほど執拗にからかわれるなんて、それ、教育実習生の勲章だとは思わないか? ひょっとしておれより、おまえのほうが教師に向いてるかもしれんぞ』
来月から教壇に立つ彼は、あたしをそうやって励ましてくれた。で、採用試験に再チャレンジしようって意欲が湧いてきたってわけ」
ひとしきり話し終えた先生は、そろそろ下に戻りましょうかとぼくをうながした。けれどもぼくは 白秋の座卓の前からなかなか離れられなかった。先生にとって、ぼくと魚津の悪ふざけはやはり許しがたいものだった。それに気づいたいまとなっては!
だが、ちゃんと謝ることができないでいるぼくを、あや子先生は赦してくださった。雷鳴とともにほとばしる光を反映して明暗が与えられた先生の面影に、ぼくは教会の聖母像をみる思いがした。
雨脚はますます激しさを増し、側溝から濁流となってクリークに注がれていた。
傘を持たない四人は水天宮前停留所まで駆けだして、出発寸前の堀川バスに飛び乗った。南筑バスだったかもしれない。西鉄バスでないことだけはたしかだ。バスの車内は、磨きこまれた木の床に雨しずくがぽたぽたと落ち、ディーゼルオイルとけばだった座席の臭いが混じりあって、むせ返るようだった。ぼくは最後部の席に陣取って、次第に遠ざかる蔵屋敷の連なりをいつまでも眺めていた。
「やー、さんざんな目に遭うた」
「まさかこぎゃん降りだすとは思わんかったね」
館外にいた明石と魚津は、とつぜんの大雨にたたられたという。ずぶ濡れになったせいか、やたらと興奮しており、ときたま大声をあげて笑っていたけれども、屋根裏部屋の余韻に浸っていたかったぼくは、とても彼らと一緒になってはしゃぐ気分にはなれなかった。
が、ふたたび西鉄柳川駅に着いたときに考えをあらためた。あと三十分もすれば先生とお別れなのだ。いつまた会えるかさだかではないし、もしかしたらこれで最後かもしれないじゃないか。ならばもっと愛想よくしようとつとめて陽気にふるまった。魚津と明石にしても、思いはきっとぼくと同じだろう、さんざん莫迦話をした。
プロ野球選手の話やクラスで気になる女の子の話など、中学一年の男子生徒らしい話題でおおいに盛りあがった。あや子先生も大口を開けて笑っていた。が、ふと真顔になって、三人の顔を見比べた。
「二年生になるきみたちの、今後の抱負を聞かせてください」
「とくべつないです。まあぼちぼちと。勉強もそれなりに」
がんばりますとは間違ってもいわない魚津だった。
一方の明石は、少し考えていった。
「やっぱり、陸上部に入部しようかと思います」
じつは明石に、岩志田も一緒に走ってみらんやと誘われていた。俊足の彼ほどではないにせよ、持久走は得意なほうだった。けれども走るのが不得手な魚津の気持ちを考えると、ここで同調はできなかった。けっきょくぼくも、とくべつ抱負はありませんと答えた。
「小さなことでもいいよ。早寝早起きとか、食べ物の好き嫌いをなくすとか」
実習期間から感じていたことだが、先生はときどきデリカシーに欠けるきらいがある。子ども扱いされるのがたいそう不満なぼくはプイとそっぽを向いた。ところが、かたくなな態度をとりなすかのように、魚津と明石は、岩志田のとりえをあれこれ列挙しはじめた。
「岩志田はピアノ弾けるじゃなかや。コードネーム拾って、伴奏つけるのが上手」
「マンガ描くとも得意。画はいまいちばってん、ストーリー運びはけっこう巧か」
「へえ驚いた、岩志田くんって芸術肌だったんだ」
先生に芸術肌といわれてぼくは赤面したが、それ以上にふたりの思いやりが嬉しかった。と同時に、わがことばかりにかまけていた自分がむしょうに恥ずかしかった。
ふたたびぼくは窓外に視線を逸らした。電車はちょうど矢部川に架かる鉄橋を渡るところだった。雨にけぶる河口の岸辺に何艘かの朽ちかけた釣り舟が繋留されていた。
大牟田駅に着くといったん改札を出て熊本行きの切符を買った。駅前広場の時計塔をたしかめると午後四時過ぎだった。漂白された昼間とはうって変わって町並みが薄墨色にくすんでみえる。それとは対照的に、夕暮れどきの駅構内は人いきれで活気にあふれていた。
「ここでちょっと待ってて」
いうなりあや子先生は小走りに駆けだした。おそらくぼくたちに持たせるおみやげを買いに、売店に走ったのだろう。思えば先生は柳川に行って帰ってくるあいだ、ぼくらに一円も使わせなかった。電車賃、バス賃、入館料。ぜんぶまとめて先生が払ってくれた。
改札前の雑踏で、所在なさげに待っていると、先生が息せききって戻ってきた。これはおうちのひとにといいながら、携えた菊水堂のカステラまんじゅうが入った手提げ袋を三人めいめいに手渡した。
しかしさっきまでの先生とは違う。どうもようすがヘンだ。
ぼくは急いてたずねた。
「先生どぎゃんしたと。顔色まっ青よ。気分が悪かとじゃなか?」
「ううん、平気」
先生はむりやり笑顔をこしらえてみせた。しかし強がりも長くは続かなかった。
堪えにこらえた感情の堤防がついに決壊したかのように、先生の双眸からみるみるうちに涙があふれた。しずくは頬を伝って床にこぼれ落ちた。先生は顔を手でおおったが、それでも指の隙間から涙がとめどなくあふれでてしまうのだった。
先生の表情をまのあたりにした三人は、ちょっとしたパニックに見舞われた。なぜ泣くのだろう。ぼくたちとの別れを惜しんでいるようではない。ほかに理由があるようだと動揺するばかりだった。
ぼくはやみくもに問いただした。
「先生、どうかしたと? 先生、なんが悲しかと?」
見かねた明石がぼくのわき腹を突き、小声でたしなめた。
「ちった黙らんや。そうせっついたら、ますます苦しかろうが」
そこでぼくはハタとわれに返った。
顔を伏せたままの先生はしばらく嗚咽をしゃくりあげていた。が、息の痞えを抑えるように胸に手を置きながら、まぶたをごしごしと擦りながら、きれぎれになった言葉を、ポツリポツリともらしはじめた。
「いまから帰るけんって家に電話したら、哀しい報せがあるって母から聞いて……
先生の大学のともだちが、事故でなくなっちゃったんだって……
これからあたし……お通夜に向かわないと。ホームまで見送ろうと思っていたけれど……ちょっと無理みたい……ごめんね、ホントにごめん。きみたちにみっともない顔みせちゃったね……」
大人が泣くのを間近でみたのは、これがはじめてだった。だからこんなときどう対処すればよいのか、判断がつかなかった。ぼくは魚津のようすを横目にうかがった。彼は父親を幼いころに亡くしている。ほかのふたりよりもいまの心境を理解できるだろう。
ぼくの依頼心が伝わったのか、魚津は三人を代表して、
「こげんとき、なんと申しあげたらよいか……」
と前置きしながら、先生に今日のお礼を述べた。
「先生。お宅まで押しかけて迷惑だったでしょうが、いろいろとごちそうしていただいて、また、柳川にも連れていってくださって本当にありがとうございます。ぼくたちが来たときにこんなことが起きるなんて、なんだか申しわけない気持ちでいっぱいなんですが……先生、どうかいつまでも、三人の〈先生〉でいてください」
先生は終始うつむき加減で、視線を床に落としていた。
魚津がいい終えると、ありがとうとポツリといった。
ぼくたちが改札をぬけたあとも先生は改札口に歩み寄って、柱の陰でお互いの姿が見えなくなるまで手を振っていた。ぼくは先生の面影をたしかめようと懸命に目を凝らした。
あや子先生はほがらかに笑っていた。泣きながら、笑っていた。
涙でくしゃくしゃになった先生の泣き笑い顔が、三十年以上経ったいまでも目に焼きついて離れない。
【Ⅴ】
この日ぼくの記憶で、あや子先生の登場する場面は、改札口が最後である。
これ以降ぼくは彼女といちども会っていない。ただし、明石とはその後も季候のやりとりがあったようである。さらに数年後、免許とりたての魚津は明石を誘って、佐賀まで山下洋輔トリオの演奏会を観にいく道すがら、大牟田に立ち寄って、結婚して姓が変わったばかりの先生と再会したそうだ。おれに内緒で勝手なことしてと不満を漏らしたところ、電話口の魚津は苦笑した。
「ばってん当時の岩志田は東京におったろうが」
「で、いま、先生はどこに住んでおらすと?」
「さあ、いまでも大牟田じゃなかろうか。もっとも三池じゃなくて、より海ぞいの町で」
魚津の口調に個人的な思い出を大事にしておきたいという意思を感じて、ぼくはそれ以上先を追わなかった。
さて、旧友のふたりはこの小説をどう読むだろう。
事実とぜんぜん違うじゃないかと注文がつきそうだ。明石など、これではおれが悪者扱いじゃなかやと激怒するかもしれないが――お叱りを覚悟のうえで、ぼくはもう一場面を書き加えようと思う。その日一日のできごとを順に追える稀有な記憶、あますところなく記録しておきたい。
そうだとも! この小説は、あやふやな記憶をとり戻す作業だ。
魚津には魚津の記憶があるだろうし、明石には明石の記憶があるだろう。ひとの数だけ記憶は存在し、しかも決して同一じゃない。面白いじゃないか。同じ時間、同じ場所に一緒にいても、まったく同じではないのだから。ぼくが忘れてしまったことをきみたちは覚えているはずだ。埋もれた記憶を掘りおこしてみたまえ。自分はこうだったぞと教えてもらえるなら、ぼくはなおのこと嬉しい。
最後に、あや子先生。
先生はあの日のできごとを覚えていらっしゃいますか?
三人に示した教育的な配慮、ほほえみを常にたやさない穏やかなたたずまい。あの日、教育実習生のあなたは、教育者であることをまっとうしました。ぼくたちにとってあなたは永遠の先生ですし、また、最初に出会った大人の女性でした。記憶のかたちは多少違えども、ぼくたちはそのことをけっして忘れておりません。
これから先したためることは、先生のあずかり知らぬことです。
これがぼくの、あの日の記憶の消失点です。
特急の通過待ちで停車中の窓を開いて、ぼくは水気をたっぷりと含んだ風に顔をさらした。福岡の雨が熊本まで追いついた。ただしいまは霧雨だ。ホームの看板に〈木葉〉と記されている。駅のすぐ裏手に小高い山が迫り、石灰質の山肌をあらわにしている。午後五時過ぎの空には夜の帳が降りて、稜線との境目は判然としない。
車内は蒸風呂のようである。不機嫌そうに押し黙るふたりに、ぼくは自分ひとりが知り得た情報を得意げに披露しはじめた。
「おれ、先生のともだち、じつはオトコって思うったい」
が、お喋りは途中でやめるべきだった。
「あがん泣いとらしたけん、先生の恋人だったとじゃなかろうか」
と、明石がやおら目を剥き、おそろしく低い声で唸った。
「知ったふうに。先生の恋人てや? なんば根拠にいいよっとや」
「いや、これはあくまでもおれの推測だけん……」
「推測? ふざくるな。もしも学校でそげんことば吹聴するなら、ぬしゃ打たるっけん!」
日ごろ温厚な明石のどこに、こんな激情が潜んでいたのか。その剣幕にうろたえたぼくは、ひとこともいい返せないでいた。
すると魚津がボソリともらした。
「岩志田。亡くなったひとのこと、あれこれいうもんじゃなか」
ぼくを見ようともせず、外に目を逸らせたままでつぶやいた。
「明石のいうごつ、おれたち三人、ホントに子どもじみとったね」
「ほんなこつ子ども子どもしとった。柳川まで観光に連れていってもろて、おみやげもろて、なんからなんまで先生にしてもろて……いったい大牟田になんしに行ったっだろか?」
――そがんこと知るもんや!
心の中で唱えた呪詛は、明石にではなく自分に向けられていた。なにゆえ、つまらない思わせぶりを口にしたのか、わずかばかりの優越感を味わいたかったのか、その心境がいまだに理解できない。
ぼくはなにもわかっていない子どもだった。そして明石と魚津は、ぼくよりも少しばかり分別をわきまえていた。しかししょせんは中学生、言い表せない思いや、釈然としない感情を、適当な言葉に置き換える術を持たなかった。せいぜいみずからを子どもっぽいとあざけるか、押し黙ってしまうかのいずれかである。だからせめて熊本駅に着くまで、無言の行を決めこむ三人だった。
一筋の光の束が、霧雨にむせぶ駅舎をオレンジ色に照らしだす。
絹を引き裂くような甲高い警笛を鳴り響かせながら、特急有明が通過していった。警笛は山の麓にはね返り、山間の町の玉東にいつまでもこだましていた。
圧縮空気を噴きだしながら自動扉が閉まると、連結器の噛みあう振動が腹の底にゴトンと伝わった。やがて、不機嫌な乗客を乗せた小豆色の鈍行電車は唸りをあげてゆっくりと動きはじめた。 《了》
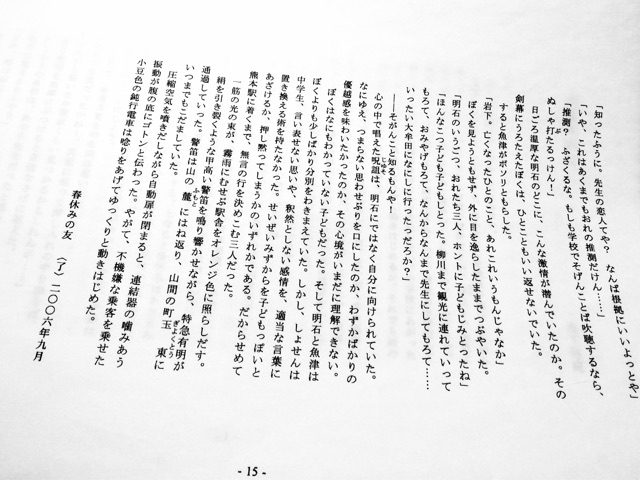
『春休みの友』 四〇〇字詰原稿用紙四五枚 二〇〇六年九月
【関連記事】
kp4323w3255b5t267.hatenablog.com