サイタマに住んでいるあいだ、子どもの入学式と卒業式に、つごう4回出席した。小学校と中学校と。
ぼくは、君が代を歌わなかった。
小学校の入学式でのことだった。式典が始まると同時に、全員ご起立くださいとのアナウンスがあった。その直後、「国歌斉唱」と、厳かな声で教頭が告げた。ははあこうやって不起立を防ぐのか、考えたもんだなと妙に納得した。
ピアノの前奏が鳴り響いた。ぼくとぼくのパートナーは、示し合わせたわけでもなく、同時に着席した。全員が席を立っているなか、椅子に座っているのだから、そうとう目立ったに違いない。君が代が斉唱されているあいだ、時間の流れが滞っているように感じた。40秒間が、とてつもなく長く感じた。ぼくは抗議を示したつもりではなかった。が、結果としてそれは、意思表明以外のなにものでもなかった。
周囲からの痛い視線にさらされはしなかった。みんな適当にやり過ごすのがサイタマ流なのだ。放っておいてくれる。教師から注意されることもなかった。式が終わった後も、何事もなかったかのように、ぼくは知り合いの保護者とことばを交わしていた。
ただ、次の日に、無言電話が幾度もかかってきた。家にいたぼくは焦れて、何度目かに、いったいどなたですか? と問うた。するとたった一言、低い男の声で「アカ」と告げられた。単純だなあ、あのねぼくは共産主義者じゃないんだよと言い返したくなったが、電話はすでに切れていた。
小学校へは、頻繁に足を運んだ。家にいることの多かったぼくは、なにやかやと役割を押しつけられたのだ。そればかりではない。行きがかり上、さまざまな問題に直面した。学童施設の校外への移転の問題。体育館の使用についての問題。争点が二分したとき、ぼくは常に学校側と対立する立場にあった。そしていつの間にか矢面に立っていた。お母さんがたに、やっぱり男じゃないとねとか、イワシさん弁が立つからとかおだてられ、校長室に赴き、直談判するのがぼくの役目だった。
まあ、札つきの親だっただろう。べつに理不尽なクレームをつけたわけではないから、モンスターペアレンツやらクレーマーやらの類ではなかったと思いたい。が、学校側や地域社会が、ぼくをどんなふうに見ていたかはわからない。変わり者だ、ぐらいには捉えていたと思う。
とにかく、そんな変わった父親のもとで、子どもは成長していったのだ。
小学校の卒業式でも、ぼくとパートナーは立たなかった。しかしまあ、キャラクターが浸透していたから、何事もなかった。せいぜい親しい保護者のかたから、イワシさんまた立ってなかったねーと指摘された程度だ。しかし、〈また〉ということは、〈前にも立たなかったのを知っている〉ことを意味する。
中学校の入学式は、少し緊張した。他の学区からも生徒やその保護者が集まっていたし、厳かな雰囲気は小学校の比ではなかった。ここでもまた同じように、全員起立の号令のあとに、すぐさま国家斉唱が始まった。おそらく県の教育委員会が作成した実施要項が存在するのだろう。県教委の指導主事と、体育館使用の問題で交渉したときのことを、チラッと思いだした。かれはぼくのことを、あらかじめ調査しているようだった。
中学校では、だから大人しくしておこうと決めた。子どものためにも、出しゃばるのは良くないと思ったからだ。学校の行事参加は、できるだけ控えた。しかし、夜のパトロールだけは、どうしても引き受けざるを得なかった。ここでもまた、男の人がいると心強いからという理由というか、大義名分があった。ぼくはお母さんがたと一緒に、懐中電灯を手に、夜の繁華街をパトロールして回った。
サイタマの、東京に隣接した街は、同調圧力といったものはほとんどなく、人はそれぞれ、口出しはしないという、風通しのよい地域だった。だから過ごしやすく、長く居つくことができた。ただ、高校の受験が近づくにつれ、わが家は悩んだ。子どもの希望は、東京の私立学校へ行きたい、だった。学力からすれば、サイタマ県K市の女子高校が妥当だったが、どうしてもそこへは通いたくないのだという。近場の公立高校も、子どもの視野には入っていなかった。わが家には(ぼくのせいで)お金がなかった。率直にいって、貧乏だった。私立高校に通わせる余裕なんてなかった。しかし、子どもの希望をむげにはできない。結局、トーキョー都K市にある私立高校を受験させた。ぶじに合格し、晴れて卒業式を迎えることができた。
ぼくは、卒業式の出席を遠慮するつもりだった。しかし、子どもから念を押された。「オトーサン、卒業式にはぜったい来てね」と。
「ぜったい来ないでね、じゃないのか」とぼくは混ぜっかえした。
「また、着席したまんまだぜ?」
「いいよ、そんなの慣れっこだから」
サバサバとした調子で答えた。
中学校の卒業式も、「全員起立」のアナウンスから始まった。ぼくとパートナーはもう、最初から立たなかった。慣れたもんだ、と自分に苦笑した。4回も不起立を繰り返したら、さすがに動揺はしない。裏声でだって歌えるものか。ぼくは天皇を嫌いじゃないし、いち人間としてはあのご夫妻を尊敬もしている。けれど万世一系を称揚する歌を、なにゆえ歌わねばならない? ぼくはまっぴらだ、断固拒否する、いままで同様、これからも。そんなことを考えているあいだに、国歌斉唱は終わっていた。
さて、子どもがどうしても出席して欲しいといった理由が、式の後半ようやく判明した。3年間無遅刻・無欠席として、表彰されたのである。ぼくはうかつにも気づいてなかった。となりのパートナーに「知っていたか?」と訊ねると、かの女は「当然」と答えた。
「でなきゃ、推薦もらえるわけないでしょ」
なるほどね。ぼくはため息をついた。おれには到底できないことだなと。
穏やかな日和の四月、高校の入学式にも足を運んだ。K駅から20分歩く、(ロックオヤジの視点からすれば*)パンタやB'zの松本が通った学校である。
入学式は、やはり厳粛にはじまった。エルガーの『威風堂々』が吹奏楽で演奏されるなか、新入生が入場するといった。が、壇上に日の丸は掲げられておらず、君が代を斉唱することもなかった。ただそれだけのことで、ずいぶん雰囲気が違う。和やかな入学式だった。これはぼくだけの感想かもしれないが、抑圧的な空気に支配されることのない式典に、5回目にしてようやく、めぐりあった気がした。
単純なもんだ。
それだけでぼくは、子どもがこの高校に進学できてよかった、と胸をなでおろしたのである。
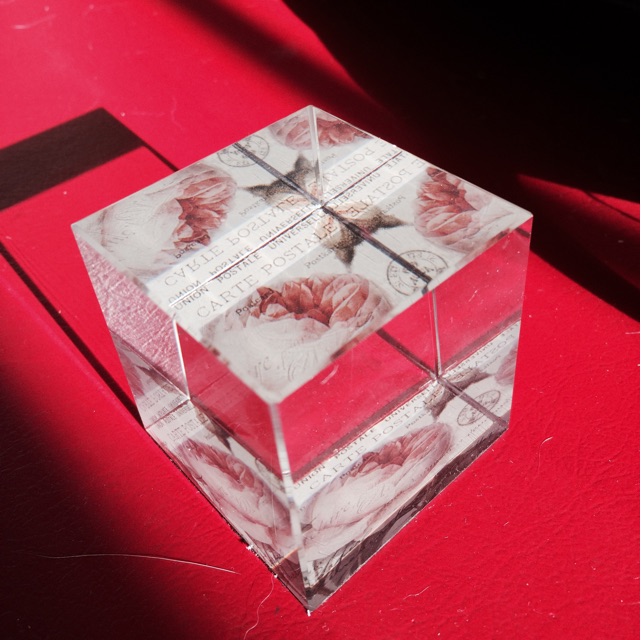 souvenir
souvenir【追記】
*日本のロック・ポップスにおいて、『君が代』を秀逸にアレンジしたものを、ぼくは3つ思い浮かべる。自由奔放なピアノ弾き語りをした矢野顕子、バカラックふうに洒落のめしたピチカート・ファイヴ、そしてパンク調でぶっちぎった忌野清志郎である。
これら3つの『君が代』は、万世一系の引力圏を逸脱しているように思える。とくに清志郎のそれは(糸井重里などに批判されていたものの)ぼくには痛快だった。間奏のベースラインが浮上し、『星条旗よ永遠なれ』を奏でるところで、清志郎が「おおっ?」と唸るあたりは、皮肉が効いていて最高だった。Char(チャー)もまた、ジミ・ヘンドリックスばりに『君が代』を弾きたおしているが、あの曲が持つ禍々しさから逃れるには至らなかったというのが、ぼくの感想だ。