震災後、久しぶりに購入した二冊の書籍について語りたい。絲山秋子チクルスである。まずは『薄情』から。

主人公の宇田川静生は降り積もった雪にコンベックススケールを突き刺す。スチール製の巻尺、メジャーのことである。現場ではコンベと略称されるが、正式名称を記すのが絲山作品らしい。事物を正確に書き表すことにより、宇田川が深雪に垂直にスケールを突き立てた様子が視覚的に伝わってくる。
雪に閉ざされた高崎の町の描写は抑制がきいており、余計な情が滲みでない。けれどもちょっとした語句の選びに、筆者の思いやりの行き届いていることがうかがえる。たとえば、ありあわせの材料で作った常夜(じょうとう)鍋を、親子がつつく場面。
単純な鍋なのに意外に食べやすかった。二人ともすいすいと箸が出た。(16ページ)
この「すいすい」に読者のぼくは安心して小説界へと没入できる。震災の後に読んでよかった。もし、それ以前に読んでいたら、絲山の透徹した筆致に潜む、細やかな機微に気づかぬままだっただろう。
宇田川は地方都市で暮らしながらも身を持て余している。とりたてて不幸な状況ではないにせよ、お世辞にも幸福だとは言えない。収入の不足をアルバイトで補う日々。夏になれば嬬恋のキャベツ畑で泊り込みの収穫作業に精を出す。しかし、こんな生活はいつまでも続かない。
漠然と不安を抱えながらも、やり過ごすしかない日常。淡々と進む時の流れに、しかし筆者は一滴の不確定要素を垂らす。群馬県高崎市郊外の、旧市内と旧郡部の境目のような地帯を、宇田川は「境界の区域」と名づける。その境界の区域に「変人工房」がひっそりと建っている。知人に同行した宇田川は、そこで鹿谷と出会う。
野武士のような風貌であった。顔も、目鼻も、掌も、全てがぐりぐりと大きかった。紹介されずに会ったら少し怖かったかもしれないと思った。(44ページ)
古典文学のような、破格の描写である。どの登場人物よりも輪郭が際立っている。この鹿谷の登場によって、宇田川の無常と思われる日々が少しずつ有に動きだす。
「変人工房」のようなアジールは、地方都市の周辺に点在する。ぼくの住む熊本も例外ではない。一見世捨て人のような謎めいた人物が、市内からちょっと隔たった場所に居を構え、店舗を開き、何事かを主宰している。熊本でいうなら、俵山の麓にある西原村だろうか。ともあれ地域という柵(しがらみ)の外側に「無縁領域」が在るのは確かだ。それだからぼくは「工房」のたたずまいを、わりと容易にイメージできる。
宇田川は、鹿谷の個性と神秘性に魅了されつつも、適当に距離をとり、深入りしないよう努める。それは「変人工房」に集う者に共通した態度で、美術家である鹿谷の創作アトリエに踏み入れるような真似はしない。そこは侵してはならない聖域なのだ。が、慎み深い態度を保ってさえいれば、「変人工房」は居心地のいい、安息を得られる場所となる。
数ヶ月の嬬恋での収穫作業から帰還した宇田川は、高崎の実家へまっすぐ帰る気にならず、工房に寄り道する。そこで鹿谷は宇田川にビールを勧め、寛ぐように気を配る。そして珍しく饒舌になった鹿谷は、宇田川に昔話を語り始める。
「昔犬を飼ってた、脱走癖があってね、ある日本気で怒って、散歩に行くふりをして行かなかった、何度もリードを持って行くふりをして、最後に自分だけ行った」と鹿谷は述懐し、「かわいそうに」と宇田川が相槌をうつと、
「帰ってきたらね、犬のかたちをした絶望がいた」鹿谷さんはそこで真面目な顔になった。「今の君は、その犬にちょっとだけ似てる」宇田川は黙ってビールの缶を手に取ったが中身は空だった。(87ページ)
巧いなあ、と思う。このやりとりなど絲山の面目躍如とも言えるだろう。簡潔なせりふの中に幾重にも意味を含ませている。読んでいて、ひりひりする。
見習いの神主である宇田川という青年に、工房の司祭である鹿谷は親しみ以上の特別な感情を抱いている。それはのん気な宇田川もさすがに察知している。しかし、その感情の源がどこから湧き出しているのかまでは分からないでいる。
『薄情』には三人の女性が登場する。宇田川の一年後輩である蜂須賀、「変人工房」でも鹿谷に一目置かれる山井、宇田川がバイト先で知り合う吉田。この中で、アジールの秩序に亀裂をもたらす存在が、蜂須賀である。離婚したのち郷里の高崎に戻ってきた蜂須賀は、工房に出入りしていた父親に伴って鹿谷と知り合うが、やがて男女の関係を結ぶ。穏やかで、お互いに深入りしない人間関係が、それにより微妙なバランスを保てなくなる。山井をはじめとした常連は、次第に工房から足が遠のく。
宇田川もある出来事をきっかけに、工房に足しげく通うことをやめてしまう。謎めいた「二人の田中」が登場し、宇田川にやんわりと警告を発する。ツイードの田中が<子どもに説明するように宇田川に話し始める>のだ。
「宇田川さんはミカンだけを見てるんじゃないんだ。ミカンを含めた環境を知る。知りたいことだけを知る。目に見えても知りたくないことは意識しなければ認識しないし、見たことがないものや、見えないものでも知りたいことは認識する」 (141ページ)
口髭の田中が続ける。
「車で同じ場所を走ってもひとの車と自分の車じゃ景色が違うだろう? ラジオつけてるのとなにもかけないのでも違う。見ているものが違うんだよなあ」 (同)
こうした、まったく思いがけないようで、じつは後になると偶然ではなかったと分かるようなめぐり合わせは、決して珍しいことではない。リアルの生活でもよくあることである。ただ、よく認識していないと、それはただの漠然とした不安でしかない。小説の暗示は、そういった不可解さを解き明かす鍵ともなり得る。読む側のアプローチによって、テキストに「あーそうだったのか!」とヒントを見出すことも可能なのだ。
宇田川は瑞穂と肉体交渉を重ねるが、かれにとって瑞穂は都合のいい相手だったし、この関係はきっと続いていくものだと安心していた(この一方的で身勝手な思いこみは男性の心理にしばしば起こりがちであるが、女性である絲山が、どうしてこれほど男性の錯誤を的確に描写できるのか、感心すると同時に、作家の想像力の凄みというものを思い知らされる)。それゆえ、瑞穂の側から一方的な別れを告げられたとき、宇田川はかれなりに「うひゃあ」と動転するが、決定的な喪失感には至らない。ただ、釈然としない思いが次から次へと内側から湧きあがってくる。
そもそも、この子のことなんて何も知らないんだ。好きな色とか行ってみたい国とか血液型とか、そんな表面的ないくつかの情報以外は(184ページ)臍(へそ)を間違えた、という気がする。なんであの子を中心に生活を回してしまったんだろもともとおれに臍なんて、中心なんてあったんだっけ何にしても、もうしばらくいいわ寝そべったままで彼は思う。(187ページ)
文末に句点(。)がないのは、間違いではない。『薄情』の冒頭から(。)抜きの行はしばしば現れる。
いつもの通りのおれとは誰なのか(4ページ)
宇田川が思いめぐらすときに、この(。)抜きが使われる。頻繁には現れない。ふつうに(。)を使った内面の吐露も多い。では、なぜ絲山は要所要所で句点を省略するのか?
それは目に見えない「 」、カギカッコで括られているからではないか?
著者の意図がなんであるか、ぼくは解説できない。マルなしとマルありの差異を分析するような野暮はしたくない。
「 」でも、《 》でもいいけれど、その不可視のカギカッコに括られた(。)なしの行にこそ、宇田川のホンネが現れているように思える。その際立ちを、絲山は控えめに書き表したかったのかもしれない。
宇田川は「変人工房」の決定的な崩落を目撃してしまう。鹿谷を司祭とする緩やかな共同体は燃え落ちてしまうのだ。鹿谷が言っていた言葉を宇田川は思いだす。「燃える可能性があるからこそ、燃してしまう」。高崎という地方都市から少し離れた位置に住む山井は、事件の当事者でもある蜂須賀を見舞うよう、訪ねてきた宇田川にそれとなく(しかし強く)促す。それはこれから何十年も、この地域で暮らしていかねばならないだろう蜂須賀に、連絡の通路を、余地を与えておくべきだとする山井の判断でもあった。
「一生に一度か二度」と山井さんは言った。一度や二度だからって許されるのか許される?いつからおれは裁いているんだ(213ページ)
緩やかな共同体と、先ほど書いた。そういう場が必要ではないかとの意見は、ぼくの周りでも、ふと思いだしたように語られることがある。いずれ私たちは否応なしに年老いていく。そのときに備えて、地縁・血縁とは別の、もう一つの共同体を構築しておくことが大切なんじゃないかしら? と。
「今回、地震のあとに思ったんだよね。水道が断水して、水が必要だってときに、いざ頼りになるのは、親戚よりも行政よりも、ふだんからつき合いのある、気の置けない友だちなんだって。あと何十年生きていられるか分からないけれども、そういう利害のないもの同士で、連絡できるような関係を築いておく必要があると思うんだ」
そこでぼくは、小説と現実の結界が、解けていくのを確かに感じる。『薄情』で語られる内容は、まったく絵空事ではなく、読み手であるぼくたちの生活意識と、地続きでつながっている。
蜂須賀と会い、温泉へ行き、今後の解決はないけれども、ひとまず自分の役割を全うした宇田川は、そのままハンドルを東北に切って、<十日ほど家に戻らなかったのである(229ページ)>。
「ネタバレ」になるので結末は書かないけれども、最後の20ページ余は絲山お得意のロードムービーである。旅の途中で青年を拾って、若さゆえの率直さに目が眩みながらも、いままでヴェールに包まれていた宇田川の、混濁した意識の薄い膜が一枚一枚と剥がれていくあたり、読んでいて爽快な気分になって、ページを捲る速度もいきおいを増す。
だんだん頭が冴えてきたぞ(247ページ)
そうだ、なぜぼくが絲山秋子の小説にこれほど惹かれるのか、何度も読みかえしたくなるのか、その理由がようやく分かった。それは適切に配置された小説の「結構」であり、ある瞬間にいきなり加速する筆先の勢いであり、心の奈辺にわだかまる名状しがたいナニモノかを操りながら、不安定な日常を輪郭線のハッキリした文章で鮮やかに切りとる筆者の、巧みのなせる技である。同時代、ほぼ同世代に、彼女のような作家のいることが嬉しい。そんな思いにさせてくれる『薄情』は、『イッツ・オンリー・トーク』からスタートした絲山式ロードムービー小説の中でも、傑作に数えられる一本である、とぼくは断言する。 (敬称略)
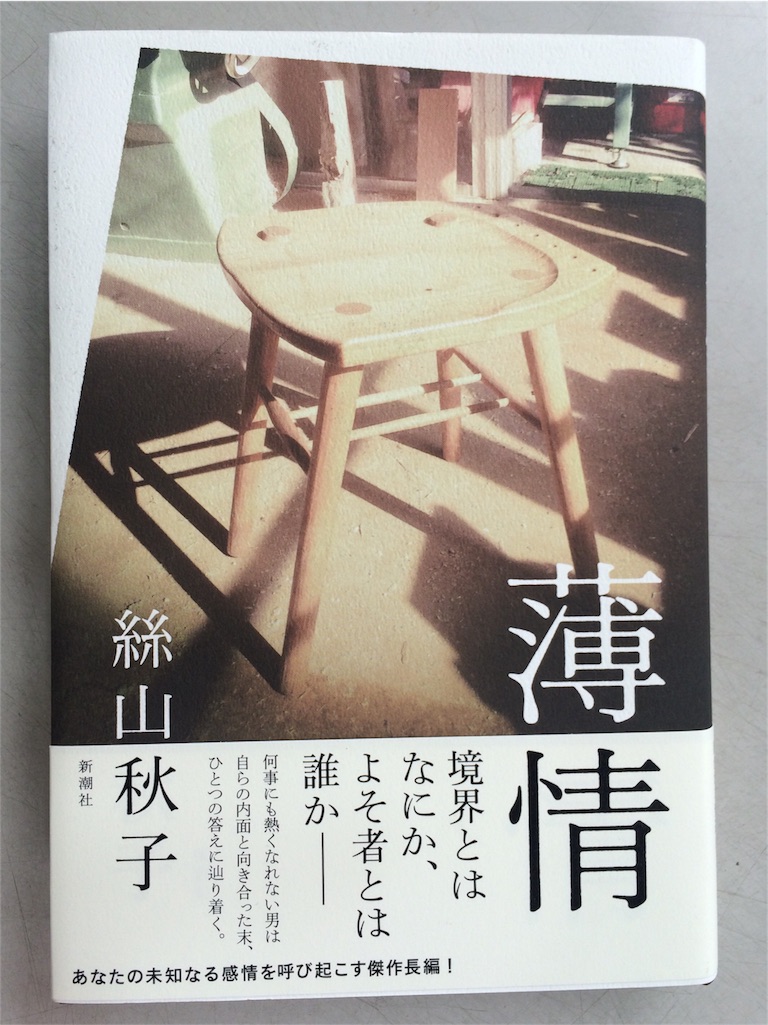
『薄情』(新潮社・2015年12月20日発行)谷崎賞受賞作